
フリードリヒ・グルダ I LOVE MOZART, I LOVE BARBARA[DVD]
M1〜M5はグルダのピアノ・ソロ。くつろいだ雰囲気だけれども真剣な演奏による、モーツァルトへの愛の告白。M5はグルダの編曲で、素敵なピアノの小品に仕上がっている。 
モーツァルト : ピアノ協奏曲第23番&第26番
モーツァルトのピアノ協奏曲の中で、とりわけ有名な23番と26番を収めた1枚。 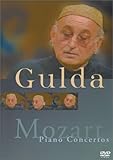
フリードリッヒ・グルダ・プレイズ・モーツァルト・ピアノ・コンチェルト [DVD]
グルダのモーツァルトには他にはない自由さがある。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第25&27番
グルダといえば何か奇抜なことをしてくるのでは?と思われがちだが、このCDでは逆に模範的な演奏である。

グルダ・ノン・ストップクラシック界からの解放を夢見たグルダ・・・。その音の響きは躍動感に満ち溢れ、感性の鋭さと生命力の強さが伝わってきます。グルダのアリアは、絶品ですよ!これこそ、究極の癒しです。 |

|
Mozart piano concerto K.488/3 Gulda-HarnoncourtMozart piano concerto (KV.488)23. A-major/3 with Gulda.Royal Concertgebouw Orchestra conducted by Nicolaus Harnoncourt,1984 |
|
Thelonious Monk/ April In Paris [Album: Thelonious Himse ... 以前聴いたピアノのCDを探してます!! 卒倒するほどの超絶バイオリン、チェロ演奏のCDを教えてください。 【中古】グルダ・ノン・ストップ/フリードリヒ・グルダCDアルバム/クラッシック 古い時代のピアニストの音源(CD) ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第5番 ≪皇帝≫/ピアノ・ソナタ第17番≪テンペスト≫ [ フリードリヒ・グルダ ] フリードリヒ・グルダはクラシック&ジャズのピアニストだったのですね。どのよう... 久々に Bach にハマる ピアニストのフリードリヒ・グルダのファンの方、お持ちのベスト盤を理由を添えて... Bon Jovi/ Something To Believe In [Album: These Days] ( ... MOZART BEST 1500 15::モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番・第27番 [ フリードリヒ・グルダ ] |
![[aTV Home] 《守護月天》 ED 桜野みねね](http://img.youtube.com/vi/CBNYO40Pu3o/1.jpg)
桜野みねね[aTV Home] 《守護月天》 ED 
ミスインターナショナルミス•インターナショナル世界大会in沖縄 開催記者会見 
The Jon Spencer Blues ExplosionJon Spencer Blues Explosion - She Said 
Duran DuranDuran Duran - Girl Panic! 
ゴウカイザーゴウカイザー プロモ 
Neverwinter NightsNeverwinter Nights 2 Gameplay HD 1 
かえるの絵本ケイトとピアノの絵本 - Kate and her piano book 
及川奈央みつばちの悪戯 及川奈央 |

[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
大寒禊行・玉前神社(千葉県長生郡一宮町)
Jennifer Lopez - If You Had My Love
ビションフリーゼ 真昼の決闘
京都大学 全学共通科目「情報通信政策論」2012年10月23日
フリードリヒ・グルダ ウェブ