
深いお話なんでしょうが、私には面白いコメディに感じました。
なかなかドギツイ台詞を単調な台詞回しで平然と連ねていく様子が面白くて仕方ない。
当時の千住や荒川周辺の閑散とした様子も興味深いです。
昔のイタリア映画に似たような、間を詰めてドンドン喋るという映画。
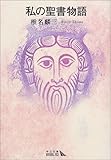
あるディスカッションの会で聖書をトピックにすることになり、急遽本箱から引っ張り出し読んで見た。学生時代、実存主義に関心を持ち、日本文学での代表的小説家とされていた椎名麟三の『重き流れの中で』や『永遠なる序章』を読んだが、そのまさに重苦しく観念的な文体に辟易したものの、その生と死、自由の意味を突き詰めようとしているひたむきさには打たれたものだった。その椎名麟三がキリスト教に入信ってのは狐につままれたような気がしていた。「結局、人間って弱いんだな」。
ところが今回、本書を通読してみて椎名麟三の信仰ってのは結構怪しいんじゃないか、ってのが発見だった。前半三分の一は無神論者からの聖書に対する罵倒に近い。「なるほどほんとにバカヤロウの本だと思った。」なんてセリフが頻発。その彼がどうして信仰に至ったのか、興味深々だったが、結局その入信の契機がどうも、象徴的でスット納得いかない。どうも聖書のキリストが復活した後、自分が生きている事を弟子達に示す為、手足を見せ、魚を平らげた下りを読んだ時に、衝撃を受けたらしいが、本書を読んでもその衝撃は理解できなかった。
信仰を持っている人には腹立たしい罵倒本、信仰を持たない人には「あれれ、何でよ?」ってな気持ちになる本です。

著者の半自伝的小説である。とはいえ徒に回顧的なのではなく、著者は主人公の少年を「僕の滑稽な死体」と呼んで客体視し、冷静な文体で物語を進めており好感がもてる。少年は家出の後コックとして働きながら悲惨な環境に耐えていくうちに、自らの血=死を盾に闘うという方法を身につけてゆく。その後、車掌となって盲目的に非合法運動に猛進してゆくが、いとも簡単に検挙され抜け殻同然の姿で生きることを余儀なくされる。少年は常に滑稽なほど単純無知でありその悲劇性すら思い込みに過ぎないのだが、それだけに、その懸命な姿は壮絶である。救いを求めて「ツァラトゥストラ」を読むものの何の答えを見出せず茫然となるラストシーンは特に印象的。観念小説だが決して難解ではなく、ごく自然に「実存」という言葉を感じさせる。
| 