
オーネットコールマンを敬愛するパットメセニーが、オーネットコールマンの強力リズム隊であるbのチャーリーヘイデン、drのビリーヒギンズと組んで作り上げたアルバムです。
サウンドの方は、後に、ヘイデンと作るアルバムから想像されると肩透かしをくらう、かなり、ジャズのメインストリーム的なアコースティックなものからスタートします。ただ、後半に入ると、PMG的エレクトリックなものに入っていきます。とはいえ、前半部分についても、じっくり聞くと、メセニーらしいgが聞けますし、ヘイデン&ヒギンズのリズム隊は、強力そのもので、メセニーらしいメインストリームへのアプローチを楽しむことができます。ただ、今の自分的には、後半が楽しめたのも事実。
とはいえ、今後も、繰り返し聞くことになるであろうアルバム。前半部分が容認できると思うメセニーファンの方であれば、買いの1枚。

20世紀の最大の遺産である。つまり音楽を変えた、1960年ごろ私は聞いたのですがその時「スフィンクスを動かした」と表現したことが有った。メルロ・ポンティーが可逆性という言葉を使ったが、それが音において’起こる’事で音が’物’と化す訳であるー今の世に一番欠けてきたことであるわけであるーと。オーネットも「一音においてさえ」、と言う言葉を発している訳ですがこれが音楽の原点である訳です。
アジアにはそのような音楽が残っています。ガムラン、中国の影絵と音楽、ベトナムの水上劇インド、アラビア、アフリカへ広がります。
西洋の音楽はグレゴリアン出終わっていると極論を言った人も居たようですが、バッハのチェロソナタで終焉していると私は思っています。
オーネットも82歳に(私は1940生)ですから10歳歳を食っています。それでも息子のドラムとベースのトリオだけで日本で最後のライブを録音して欲しいものです。このcdの再現をしてくれれば、もう一度の「世紀の転換」の念押しと為ります。

本作はメセニーが、オーネット・グループの一員として参加経験のあるヘイデン(b),ヒギンズ(ds)と組んだトリオによる83年11月の録音。
First Circleの3ヶ月前である。
全曲中3曲がオーネットのナンバーということで有名であるが、オープニングのLonely Womann(オーネットのものとは同名異曲)に惹かれるか否かで当アルバムの好き嫌いが分かれるであろう。エレアコであろうか、メランコリックな響きのマイナー・キーによるスローナンバーに時折どっぷりと浸かりたくなるのである。6曲目は哀愁味がさらにいや増す曲調であるが、ソロは「ついておいで」的なギター・シンセによるスペイシーな展開・・
アルバムトータルとしては前半はメインストリーム・ジャズ系、後半はOfframp的なエレクトロニクスを多用したフリーキーな展開を含む曲群。もちろんオーネットのナンバーも楽しめるが、メセニーのメインストリーム的アプローチが耳に新鮮なアルバムである。
個人的にはOfflampをしのいで聞く機会の多いアルバムである。
なお85年12月のSong Xではオーネット自身との競演を聞ける。

近年でこそベーシストがリーダーのアルバムは珍しくなくなったが、50年代、60年代まではチャールス・ミンガスなど一部の例外をのぞいて、ベーシストがリーダーとなってアルバムを製作することは稀であった。それだけ脇役だったベースが、単なるタイムキープの役割から、重要なポジションになってきたところに、モダンジャズのリズムの変化やインタープレイといった複雑化との関連を見ることもできる。しかし、それ以前にオスカー・ペティフォードやレイ・ブラウンなどのバーテュオーゾの存在によってベースの重要性は認識され、50年代半ばのポール・チェンバースの台頭によってベースの可能性は拡大されていった。西海岸における最も重要で実力のあったレッド・ミッチェルの場合も、数々のセッションに名を連ね、名盤を量産していったわけであるが、決して表に出るわけでなく、この数少ないリーダーアルバムでも、特に自己名義のアルバムらしい野心などは感じられない。それでも重厚で手堅いテクニック、リズム感覚の確かさは群を抜いていて、モダンベースのパイオニアの一人として名を連ねる存在となっている。このアルバムにおけるリラックスした居心地の良さは、西海岸、コンテンポラリーが似合うミッチェルならではのものであろう。
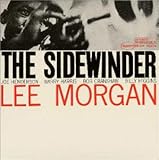
いわゆるジャズ・ロックという現象を引き起こし、ジャズ・アルバムがビルボードで上位にランクされることを実証した記念すべきモーガンのヒット曲。表題曲Sidewinderがあまりにも有名だが、全曲彼のオリジナルで巻き返しを狙った意欲作でもある。モーガンに関しては早くから天才少年と呼ばれ20歳そこそこで恐るべきテクニックと表現力を見せ付けていたが、ハード・バップやファンキー ブームが去り、時代がフリー・ジャズや新主流派と呼ばれるモード奏法を取り入れた60年代に入ると、モーガンよりもフレディ・ハバードの方がスマートでフレキシブルなトランペッターとして多くのセッションに名を連ねることになる。そんな折、起死回生を狙い、打って出たのが本アルバムであった。ブルーノート4000番台でも最も売れたばかりか、ジャズ・アルバムとしても破格のヒットとなった。しかしこの路線で当てたことで得た名声や富と引き換えに、モーガンの歌心や持ち前のジャジーでスリリングな感覚はやや遠ざかってしまった感があったことも事実であろう。その後は模索を重ねながら駆け抜けるように34歳で逝ってしまったモーガン。輝かしさと寂しさを感じさせる最大のヒット作である。
| 
