
観たくて待ちわびたノーカット完全版、即買いました。完全版の方も長さを感じさせないテンポ感で より物語がわかりやすく 歴史や時代背景に以前にも増して 興味がもてました。近々 北京に行き 紫禁城など 観光する予定です。

ナポレオンファンは日本にも一定数いて、私自身もナポレオンファンであり、ウェリントン公爵に対しては「あんなのに負けたなんて」などという様な感情しか持っていませんでした。
本書は、ウェリントン公爵を持ち上げすぎ、ナポレオンの悪いところばかりを指摘している様な印象もちょっとあります(ただし、それぞれの欠点、長所もある程度書かれています)が、そこは脳内補正をかけて読んでも「なるほど、このことのゆえにウェリントンは勝ち、ナポレオンは負けたのだな……」と得心のいくものになっていると思います。負ける方には負けるだけの理由があり、勝つ方には勝つだけの理由があった。ナポレオンは人間を大事にせず、責任転嫁をする癖があった。ウェリントンは部下を大事にし、自ら責任を引き受けた。
城山氏の意図は、人間が生きていく上での(あるいは組織運営の)参考に、この本が非常になるという事なのでしょう。
私自身はこの本を一度読んだ後、読み返す内にウェリントン公爵に対して非常に興味を持ちましたし、また、ナポレオンがなぜ負けざるを得なかったのかを知りたい人にとっても良いでしょう。
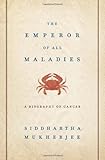
エールリッヒが発見したサルバルサンによる梅毒の治療が化学療法の嚆矢であるとされが、癌の化学療法の始まりはいささか特異な経緯がある。1943年第2次世界大戦中のイタリアの港に停泊していたアメリカの輸送船に対して、ドイツの攻撃機が爆撃し、中に積んでいた毒ガスであるマスタードガスがまき散らされアメリカの乗組員と周囲の住人に大きな被害が出た。白血球減少に陥った人が多く、事件を調査したイェール大学の GoodmanとGilman(薬理書で有名)はこれにヒントを得て、悪性リンパ腫の患者にナイトロジェンマスタードを投与し、一時的な寛解を得た。しかしこの事実は戦後まで隠されていた。著者のSiddhartha Mukherjeeはoncologist(腫瘍専門医)で手術(主に乳癌)やX線治療の話もあるが、癌の化学療法の話が中心である。戦後、小児の急性白血病(ALL)に対して葉酸拮抗剤が使われたのを皮切りに、多剤併用療法へと発展し、白血病が治癒するまでになったが、化学療法はついには固形癌(乳癌)に対して、自家骨髄移植と大量化学療法を行うところまで突き進んでいった。しかしこの話は南アフリカの医者が都合のいいデータを捏造したところでオチがついた。これは癌手術においてハルステッドのradicalmastectomyのように、しだいに拡大、過激な方向に進んでいったことを彷彿とさせる。癌研究の予算獲得と寄付募集のキャンペーンはいかにもアメリカらしいエピソードである。発癌物質の発見は19世紀ロンドンの煙突掃除人に生じたススによる陰嚢皮膚癌が始まりであるが、なんと言ってもタバコが癌予防の最大の問題である。巨大資本であるタバコ会社との発癌性や広告にたいする法廷闘争と、マンモグラフィーによる癌検診の有効性の話は医療関係者であれば知っておくべきである。後半は発癌ウイルス、フィラデルフィア染色体、oncogene、suppressor gene などの基礎的なことから分子標的治療薬のハーセプチンやグリベックの話になるが、脳みその古くなった私には少々難しい話である。この本は同じく癌関連のThe Immortal Life of Henrietta Lacksと並び2010年に読んだ医学関係の本の中で最も読み応えのあるものでした。
| 

