
バッハマン/ツェラン往復書簡 心の時
ある意味でこれは戦後のドイツ文学のなかで最も恐ろしい本である。
男は詩で名をなした。
だがその詩は戦中のユダヤ人虐殺に関わるものだったので、男は周囲からの心ない誤解によってやがて壊れていく。
かつて恋仲にあった女は、男の妻といっしょになって、破壊を食い留めようとする。
だがその男は聞く耳をもたない。
男は自殺する。
女と妻は男の死後も、励まし合っていく。
女のほうが男よりも強かった。
だがそんな男を守ろうとする女のけなげさに絶句するしかない。
結局は投函しなかった191番目の手紙が辛い。
(きわめて丁寧なこなれた訳だが、あともう少し工夫(とくに編者解説)がほしかったので-1。
例1
―は――にしないと読みにくい。
例2
279ページ 主文−複文、主語−述語が、分かりにくい
私は、あなたが私を一人の信頼のおけるアンチ・ナチという役割に還元するのではと、少しばかり危惧しています。あるいは一人の信頼のおけないそれという役割に、もし私がこのブレッカー批判にあなたが期待するように反応しなければ。
訳者の本格的な著書が読みたい。)
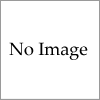
Kramer vs. Kramer [VHS] [Import]
子供のころは、自分が無力で大人の助けナシには生きていけないことを知っていた。同時に母親が自分を捨てるなどということは絶対にないと信じていた。だからいつも全力でわがままになれた。眠いときはTPOを考えずにとにかく寝たし、気に入らないときは理不尽に駄々をこねて、その場に座り込んだ。
ビリーのママは突然彼を置いて出て行った。また明日の朝会えると思って安心して眠りについたビリーは、朝起きて、ママがどこにもいないことを発見する。大きなショックが彼を襲うが、どうやって表現していいのか分からない。毎日を不安に過ごしながら、恐る恐るパパに八つ当たりをしては、またおいていかれるのではないかと危惧するビリー。典型的な仕事人間であり、家庭などまったく顧みなかったパパは時に怒りを爆発させながらも最後にはビリーに約束をする。「おまえがどんなに嫌がったとしてもパパは必ずそばにいるから」。そうしてお互いの痛みを共有しながら、パパとビリーは一緒に暮らす。日々の些細な事柄を通じて、相手に対する思いやりの深さに気がつく。
パパとママは、映画の中の90%の部分ではお互いを傷つけあっている。けれども、残りの10%で発揮してくれたやさしさにほっとする。
全編通じて派手さはないけれど、素敵なラストシーンを見終わった後にじんと余韻の残る映画。

インゲボルク・バッハマン全詩集
バッハマンは20世紀に活躍したオーストリアの女流詩人です。同じく詩人のパウル・ツェラーンとの恋愛で有名のようです(私は、ツェラーンの名前はユダヤ系ドイツのノーベル賞詩人ネリー・ザックスとの交友で知り、バッハマンとの関係は今回初めて知りましたが)。
詩風の印象としては、ネリー・ザックスや、チリのノーベル賞詩人パブロ・ネルーダの初期の純粋詩と似ている感じがしました(ザックスとは交友があったようで、本作中にはザックスに捧げる詩が収録されています。また、高名なロシアの女流詩人アンナ・アフマートヴァに捧げる詩というのもありました)。バッハマンの作品は、詩の基本色として夜というか暗闇を連想させられるので、悲痛で見極めがたい、近寄りがたい感触がするのですが、よく読むとそこには人間の尊厳というものの希求、また何ものにも消されえぬ真実への信頼と執念とが、かすかな希望の星への厳しい祈りのような必死の光を放っています。
詩自体は難解で、聖書や神話中の人物やエピソードを別の表現で暗示していたり、バッハマン独特の視界や比喩表現で対象を表しているので、一読してすぐ意味が取れるということはまずないと言ってもいい位だと思いました。しかしそれでも彼女の詩を「何かいいな。読みたいな」としぶとく眼を凝らし耳を澄ませたくなるのは、難しいイメージの皮膚の下に、ナチス台頭下のオーストリアで詩人としての使命を放棄せずに言葉による戦いを貫いたバッハマンの、不屈のヒューマニズムの鼓動と熱い血潮を感じるからだと思います。
ナチスのプロパガンダに使われてしまうような、耳当たりの良い紋切り型の言葉や言い回しに対して強い警戒心と抵抗を感じ、独自の言語表現を追及したバッハマン。日本でも戦時中は、作家の<平和>という言葉さえもが軍のまた戦争の正当化に利用された事実があります。困難な状況の中で為された詩人の厳しく粘り強いペンの闘争に対して、深い敬意を感じずにはおれません。
ツェラーンとの往復書簡も出版されていますので、興味のあられる方はそちらもぜひ。






