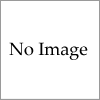
スターリングラード【日本語吹替版】 [VHS]
経済ボケ・平和ボケしている日本人に必見の映画だ。この映画は、戦争に対する甘い幻想を打ち砕く威力がある。あまりに剥き出しの人間の残酷さ・狡猾さに、妙に納得してしまった。そしてこのスターリングラードで行われた激戦は、独裁国家ドイツの敗北を決定づけた戦闘である。しかもドイツが勝っていれば、独裁国家ソ連は崩壊したはずの重要な戦闘である。
この映画の印象は、戦争という極限状態における「人間の狡猾さ」だけではない。それは、死を予感した人の「愛への逃避」と、死に直面した人々の「生物学的な性欲」である。まさに人間の隠されたありのままの姿が、戦争という極限状態で剥き出しになっている。人間の狡猾さを感じさせた場面は、赤軍将校が物理的に不可能な突撃させて殺すことで時間稼ぎをする。そしてたまらず撤退する兵隊を貴重な機関銃で見せしめに虐殺したことだ。機関銃が、小銃のみの兵隊を虐殺するだけの無意味な兵器に見えた。この味方への戦法は、モンゴル帝国の後継国であるロシアや中国なら納得である。しかもドイツはソ連人の奴隷化を実行していたので、ソ連兵に味方などいない状況であった。この極限状態で、ドイツ兵はソ連の女を強姦し、ソ連兵は女性兵士や市民と乱交していたはずだ。そこまで描写されていなかったが、人は死を予感すると異常に性欲が高まるものらしい。だから無法状態であることも手伝い、戦地での強姦が高まるのである。しかし主人公とその上司は、乱交をすることもなく、一人の才色兼備な女性との愛の争奪を行った。彼は、スターリングラードに向かう鍵のかけられた列車で、その女性を一目惚れする。そしてこの「癒しの愛」が、殺伐とした剥き出しの人間性を描く映画の印象を中和してくれる。

ライブ・アット・トップ・オブ・ザ・ゲイト (Live at Top of the Gate) [2CD] [日本語帯・解説付/輸入盤]
Bill Evansマニアとしての感想です。
とてもわくわくしたのは、音質も面もありますが、どちらかというと演奏内容と曲目でした。それは、
1.「枯葉」の演奏ででEvansの2コーラスのアドリブソロがあります。60年代後半から70年の演奏では枯葉は、演奏するにしても、ライブ音源を聴く限り、ベースソロ専用の曲となっており、Evansのソロがありませんでした。Portrait In Jazzの「枯葉」におけるScott Lafaroとのピアノ−ベースのインタープレイで多くのJazzファンを驚愕させ、直後は、「枯葉」の演奏をし過ぎた反動なのでしょうか? Scott Lafaro存命中の1960年のBirdland Sessionsでは、二人の「枯葉」でのインタープレイが演奏が何回となく、収録されており、演奏し飽きるくらい演奏をしたのではと想像されます。今回の録音では、ベースソロの後にEvans2コーラスの激しいソロが楽しめます。アルバムWhat's Newの「枯葉」が思い起こされます。なお、DVDでは1966年ノルウェーのオスロでのEddie Gomez加入直後のライブがあり、ここでは「枯葉」の演奏でEvansのソロがやはり2コーラス聴けます。
2.私の知る限り、Trioのライブでは発表されたことのない珍しい曲があります。
Turn Out The Stars、Nardis、Quiet Now、Walts For Debby、Very Early等、Evansのライブ盤を購入すると必ず収録されているレパートリーというものがありますが、Here's That Rainy DayはAloneでのピアノソロがあるだけで、Trioでの演奏はこれが初めてかと思われます。同様に、Portrait In Jazzに収録されていたWitchcraftのTrio演奏も珍しいですね。また、My Funny ValentineはJim HallとのDuetが有名ですが、やはりTrio演奏は珍しいのでは?YesterdaysもEvansのかなり初期の録音にはあると思いますが、Scott LaFaro以降のBill Evans Trioとしての演奏は聞いたことはなかったですね。Gone With The Windも以前にTrioで聞いた記憶がありません。
3.晩年のEvansは、激しくAggressiveな演奏がなく、クール過ぎると言われるのを意識し、ミスタッチがあろうと構わず激しい演奏を意識していた
ようですが、今回のTop of The Gateのライブは、音質のこともありますが、十分に感情的で激しい演奏になっていますね。また、この時、Eddie Gomezは加入して3年程度経過をしており、すでにEvansとのコンビネーションはしっかりと構築されているようです。Marty Morellは加入直後ということで目立ちませんがTrioの演奏を壊すことなく、しっかりとしたバッキングをしている印象です。
最後に音質ですが、
現在なら、多チャンネルのデジタル録音で、各楽器に何本ものマイクを付けて良質のライブ録音盤を作るのかと思われますが、この実況録音は、録音をしたジョージ・クラビンの話にも出てくるように、professional 2-track recorderでの録音だそうです。逆に、このおかげで、実際トリオのど真ん中に座って聴いているような、とてもエキサイティングは録音になっていますね。ピアノもベースもドラムもそれぞれの音の特性を自然に再現しており、良い音質のライブ録音となっています。久々に手にするのが待ちきれないわくわくしたEVANSの実況録音盤でした。

Barbarians at the Gate [VHS] [Import]
有名なビジネス書『Barbarians at the gate』のケーブルテレビ映画化版(1時間50分弱)。
1989年に起こったRJRナビスコ社の買収劇を皮肉たっぷりのコメディとして描いている。ナビスコ社の株価低迷に頭を悩ませていたロス・ジョンソン社長は無煙タバコ「プレミア」のデビューに大きな期待をかけていた。しかし莫大な研究開発費をかけて誕生した「プレミア」はブキミな味のする失敗作だった。ジョンソン社長はマネジメントバイアウトを決意する。しかしディール約定前に噂を聞きつけた他社が買収競争に名乗りを上げる。買収合戦は途中から「競争の為の競争」の様相を呈し、ビッドはどんどんつり上がる。結局LBOの老舗・KKRがジョンソン社長側との激しい株買付け競争の末に買収に成功。しかし同時に50億ドルのジャンク債を含む200億ドル分の長期負債をナビスコに負わせる事になる(その顛末までは映画は描かない)。
メディアを巻き込んだ買収劇フィーバー、敵味方入り乱れた丁々発止、長い原作本をどんどんはしょって上手く料理している。原作ではファーストボストンの参戦など他にも面白いドラマがあるのだが、二時間に満たない時間枠なのであくまでジョンソンとクラヴィスの対決に的が絞ってある。個人的には、R.J. レイノルズやナビスコといった(1985年に両社が合併してRJRナビスコ)「従業員=地域コミュニティそのもの」的な世界が法人税制を逆手に取った新手のマネーゲームの中で変質していく様子を捉えた原作と比べるとやはり物足りないものはあった。
ジェームズ・ガードナー扮するジョンソン社長が愛嬌たっぷりの憎めないキャラになっているが、原作ではこんなキュートな人間だったかなぁ、だいたいあの人物に愛社精神なんてあったけかなぁ、と思いつつ、原作のままじゃ観客に好かれないだろうし。クラヴィス役のジョナサン・プライスは不気味で迫力がある。それにしても出演者がこうもタバコをプカプカする映画は久しぶりだった。タイトルの「barbarians」は禁煙推進派のことだったりして…。

Piper at the Gates of Dawn
ロックの歴史的には、ジミ・ヘンドリクス、ブルー・チアー、グレイトフルデッドや13th・フロアー・エレヴェイターズ(ロッキー・エリクソン)、レッド・クレヨラ、マザーズ・オブ・インヴェンジョン(フランク・ザッパ)らと並ぶ「サイケの古典」バンドと位置付けられることが多い、シド・バレットが唯一全面参加した初期ピンクフロイドのデヴュー作品である。
しかし、単に演奏スタイルや楽曲、あるいはメッセージがユニークであるという以上に、「異常な世界をまざまざと見せつける(聴かせるだけではなく)」と言う意味では、これ以上の作品はない。たぶんこれからも、ないだろう。
シド・バレットとメンバー達が幻視し具現化した、青白くナイーブで、とろけるまでに甘美、そしてどこまでも妖しく畸形的な音世界は唯一無比な試みだろう。決して60年代という時代性や、ロックというジャンルのみで片付けられてしまう安直な作品では決してない。
シドの弾く大胆かつ巧妙なエレキ・ギターのプレイには、自分の内面世界のもっとも深く根源的な、闇の部分をむき出しにされるような思いがする。非常に危険な劇薬のようにも作用する作品だ。
当時、メンバーの一人は「バンドは、シドがいれば他はだれでも良かった」と自嘲的に語っていたが、そんなことはない。リック・ライトの東洋的フレーズのオルガン、ロジャーのベース、ニック・メイソンのパーカション、どれを取っても斬新なサウンドで意欲とエネルギーに満ち溢れている。
個人的には、新バージョンが出るたびについ買ってしまう稀有なアルバムでもある(苦笑)。そしてそのたびに感動してしまう作品なのだ。
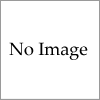
野蛮な来訪者―RJRナビスコの陥落〈下〉
80年代後半の当事、史上最大の企業買収と話題になったKKRによるRJR買収ドキュメント、原題 "Barbarian at the Gate" の邦訳、
本書同様に平成初頭の邦訳出版以来、長く絶版状態だったやはり1980年代のウォール街内幕ドキュメントの名作「ライアーズ・ポーカー」マイケル・ルイス著はいつの間にやら他の出版社からめでたく復刊しています、
出版社の性格を考慮すれば本書の復刊はとても望み得ないわけで、こころあるビジネス書出版社による復刊が望まれるでしょう、本書は新刊発売時、上下2巻で4000円という高価さが災いして古書の流通数が少ないのも困った現実、ぜひ文庫本として残して欲しいと考えます、本国ではもちろん現在までロング・セラー、
本当に現実に起きたこととは思えないような波乱万丈の企業買収劇が美にいり細にいり描写されているのは現在のビジネス・ドキュメント本の優れた典型です、
こんな本を一冊でも読んでおけば今回のリーマンB騒動などずいぶんと児戯に近くおもえ、加えてマスコミが自分たちの商売のためのニュースソースとしてどれほど大きな金融不安を期待しようとも国家としてのアメリカが他国を圧倒する金融システム維持能力を持っていることにも気付けるはずです、
日本においてはうちの会社に買収なんか関係ないとたかをくくっている企業経営者ほど読むべき本かもしれません、







